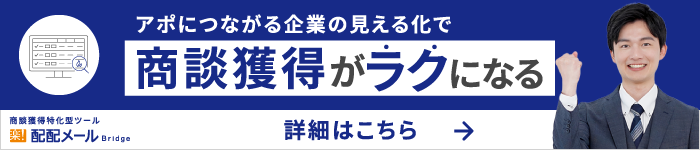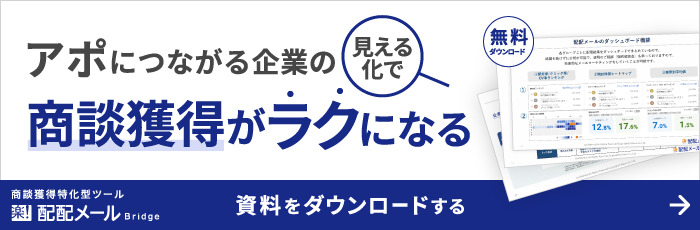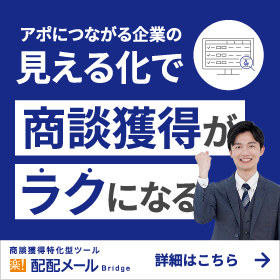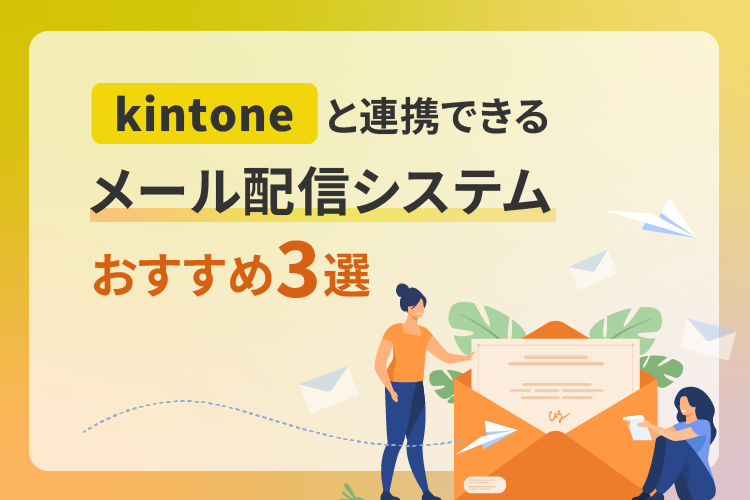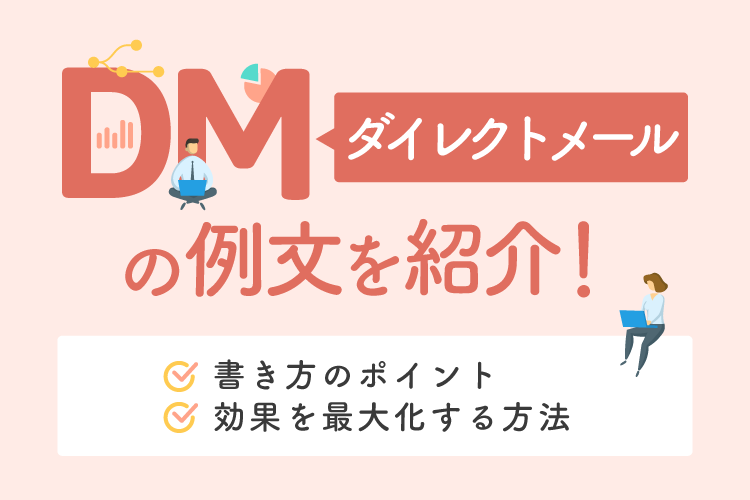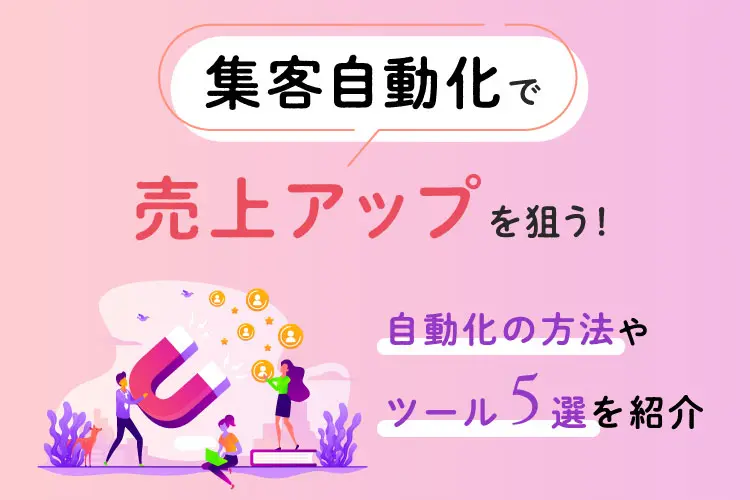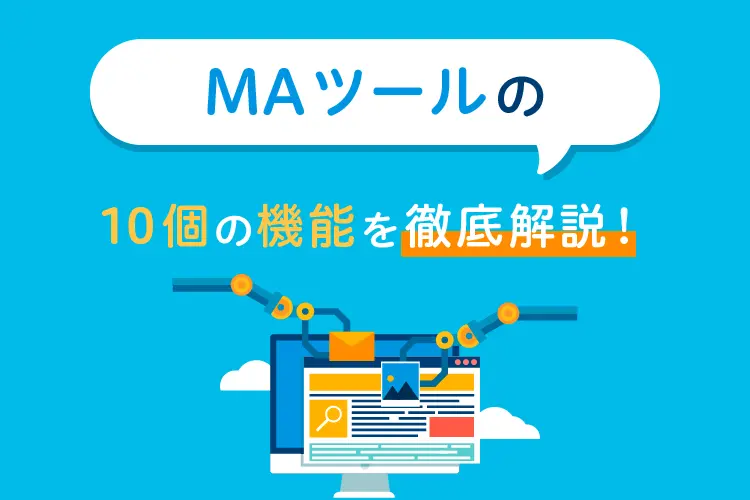MAツール検討の軸となる「導入の判断基準」と「機能」とは

MAを導入検討する際、機能面に着目する担当者は少なくありません。ですが機能面にばかりフォーカスすると、導入後に適切な運用ができなかったり、思う成果が得られなかったりする恐れがあります。本記事では、予め注意したいMAの導入判断基準と活用方法をご紹介します。
目次
MAとは?
MAとは、マーケティング領域におけるリードナーチャリング(見込み客の育成)とリードスコアリング(確度の高い見込み客を精査)の業務を支援するツールのことです。これらを自動化することで、業務負担軽減や見込み客獲得数の向上、営業利益向上が期待できます。ツールによってはリードジェネレーション(見込み客の創出)までカバーしますが、メイン機能は上記2種類と考えて相違ありません。
MAが担う領域は、デジタルマーケティング施策の一部です。営業活動の支援がメインとなるため、市場調査やマーケティング戦略の立案はマンパワーで行います。よって、全てのプロセスが自動化されるわけではないことに注意してください。今一度MAについて深く知り、“オートメーション”による恩恵を学ぶことから始めてみましょう。
MAの導入判断と活用方法

MAは機能面での評価も大切ですが、まずは自社の活用レベルに応じて導入検討するのがおすすめです。ここでは、MAの導入を見極めるポイントと想定される活用方法をご紹介します。
1.導入判断
MAの導入判断に明確な基準はありませんが、「大量のリード件数が社内に放置されている」、「リード獲得数が多くセールス担当者だけでは捌けない」といった状況下にある場合、導入検討を進めるべきです。MAを検討する良きタイミングといえます。
さらに具体的な例を挙げてみます。例えば、「社内の顧客リスト数が10,000件以上」ある場合、MAの導入をおすすめします。逆に顧客リストが10,000件を下回るならば、MA導入によるメリットが得られない可能性があります。他のツールやサービスを活用し、異なる角度からアプローチをかけた方が効果的です。
ここで「顧客リスト10,000件」に指定した理由は、MAで案件化を目指す際に、少なくとも10,000件以上のアプローチ対象が欲しいためです。一度、多くのMAがコミュニケーションチャネルに活用するメールでシミュレーションしてみます。
まず、10,000件の顧客リストに対し、MAで2通のメールを配信するとします。2通目のメールを開封したユーザーを確度の高い見込み客とし、セールスに引き渡します。なお、1通目のメールは顧客リスト10,000件に対して一斉配信します。
実際に配信した結果、1通目のメール開封率が15%、クリック率が3%だったとします。これにより、2通目を配信する顧客は、「10,000件(送信数)×15%(開封率)×3%(クリック率)=45人」まで絞られます。
続けて2通目を配信します。ホットリード(自社製品やサービスに興味があるユーザー)が残ったと仮定して、メール開封率30%、クリック率4%でシミュレーションします。最終的に残るユーザーは、「45(送信数)×30%(開封率)×4%(クリック率)=0.54人」です。この結果から、メール2通あたりに期待できるリード獲得数が1人を下回ることがわかります。
このような状況においては、MA導入するメリットが薄くなります。他のツールやサービスを導入検討するのが無難です。MAに近い導入効果を求めるならば、Bridgeというサービスをおすすめします。
こちらは配配メールが提供するメールマーケティング特化プランであり、MAと共通するさまざまな支援機能を備えています。代表的なのが、配信メールを開封、クリックしたユーザーを自動的にリスト化するホットリード抽出機能です。また見込み客のアクション(Webページの来訪など)に対し、自動的にメールを配信するトリガーメール機能もあります。
いずれにしても、MAに求めていた機能をBridgeひとつで賄える可能性はあります。「自社にMAの導入は無理か」と悩むのではなく、他のサービスもしっかりと検討すべきです。
2.インバウンドマーケティングに活用

顧客リストなどの条件を満たした場合、どのようにMAを活用するか考えます。まず挙げられるのがインバウンドマーケティング(以下、インバウンド)です。インバウンドとは、自社の見込み客に対して有益なコンテンツを提供し、商品やサービスのコンバージョンへと促すマーケティング施策です。
MAのインバウンド活用を検討する際、まずは成果シミュレーションから始めます。ここでいう「成果」とは、MA運用で獲得する月間想定受注件数に成約単価をかけた「売り上げ」を指します。なお、月間想定受注件数は、「Webサイト月間平均ユニークユーザー数(UU)×Cookie特定ユーザー来訪率×ターゲット来訪率×営業対応率×商談化率×受注率」で算出します。
一例として、仮の数字でシミュレーションしてみます。Webサイト月間平均ユニークユーザー数を3万、Cookie特定ユーザー来訪率を5%、ターゲット来訪率を30%、営業対応率を30%、商談化率および受注率を10%とします。この場合、「3万UU×5%×30%×30%×10×10%=1.35(月間想定受注件数)」となります。
仮に1件あたりの成約単価が300万円ならば、「300万円×1.35=405万円」の売り上げになります。また粗利率を50%で計算する場合、202.5万円程残ります。粗利からMAの月間運用コストと人件費を差し引き、それでも利益を残せるかが判断基準となります。できるだけ多くのターゲットでシミュレーションし、運用コストに見合う成果を得られるか確認してください。
3.アウトバウンドマーケティングに活用
アウトバウンドマーケティング(以下、アウトバウンド)への活用も検討します。アウトバウンドとは、潜在顧客に対して能動的なアプローチをかけるマーケティング施策です。ダイレクトメールやテレビCM、展示会や折り込みチラシといったプッシュ型の手法を用います。
具体的な活用方法として、ユーザーのフィルタリングが挙げられます。例えば、反応率が悪いユーザーに対して定期メルマガを配信します。MAがユーザーをスコアリングし、「全く商材に興味がないユーザー」と「反応率こそ悪いが商材に興味がありそうなユーザー」にセグメントわけします。アクションを一切起こさないユーザーはふるい落とし、商材に興味のあるユーザーだけを残します。
「反応率こそ悪いが商材に興味がありそうなユーザー」には、資料やカタログを添付したメールを送信します。これらが商材理解を促し、ユーザー側からアプローチしてくる可能性を高めます。なお、最初からカタログを一斉送信する方法はおすすめしません。ユーザーが「しつこい」「うっとおしい」と嫌悪感を抱き、購読停止に繋がるリスクが増えるためです。
関連記事はこちらメール配信サービスからマーケティングオートメーションツールへの架け橋に
関連記事はこちらMAツールってどれがいいの? 比較の際に考えるべきポイントをご紹介
MAの機能
上述にて導入判断の基準や活用方法をお伝えしましたが、ここでは導入判断に関わる機能面もご紹介します。
フォーム機能
自社のWebサイトからお問い合わせをいただくうえで必須なのがフォームです。MAではこのフォーム機能を有しているサービスが多いです。フォーム機能がMAに付帯していることでセミナーの集客フォームといった新たな施策にも転用しやすくなったり、後述の顧客管理の容易さにつながったりします。
配配メールBridgeにはこのフォーム機能が付帯しております。入力項目は自由に設定することができたり、問合せ完了後のお客様へのメールもオリジナルで作成できるなどカスタマイズ性が非常に高いです。
また、フォーム入力が完了したお客様の情報は配配メールBridge内の配信グループと連携することができるので、入力完了後に一定のアプローチをしたいというお客様にもオススメの機能となっております。
関連記事はこちら配配メールBridgeの「フォーム機能」
顧客管理機能
フォームによって取得したお客様の情報を管理できる機能も重要です。ただ、どの程度管理したいのかによって各サービスの仕様が異なります。例えば指定したフォームを通過したお客様に関してはこのグループに連携する、といった連携による顧客管理が可能なサービスもあれば、Webサイト上での行動を蓄積することができるといったサービスまで幅広く存在します。取得したい&活用できる情報を吟味したうえで自社にあった顧客管理ができるサービスを選定しましょう。
データ分析
MAには一般的な機能としてメール配信機能が存在しています。その他にも顧客管理にて述べたようにWebサイト上での行動を蓄積できるMAもあります。これらのデータを活用するためには分析する機能が必須となってきます。顧客の属性や興味・関心などから条件に合う顧客のセグメント化や、オンライン上の各マーケティング施策を一気通貫で確認するための各種マーケティングツールとの連携、各KPIのダッシュボード化など様々な分析機能がありますので、なにが必要な分析機能かを十分に検討したうえで選定することをおすすめします。
まとめ
MAは、社内における活用レベルを見極めて導入検討することが大切です。顧客リストなどの条件次第では、MAの導入が負担となるケースも考えられます。期待する成果が得られるのか、今一度シミュレーションしてみてください。

商談獲得に特化した「配配メールBridge」は、初心者でも簡単に新規顧客開拓を始められるMAプランです。
シンプルな設定画面と専門知識不要の操作で、誰でもすぐに使い始められます。さらに、専任担当による無償の導入活用支援や、充実のアフターフォローで、安心してご導入いただけます。
導入企業様の成功事例や改善要望を活かし、常にアップデートしていくことで、お客様の成果最大化に貢献いたします。